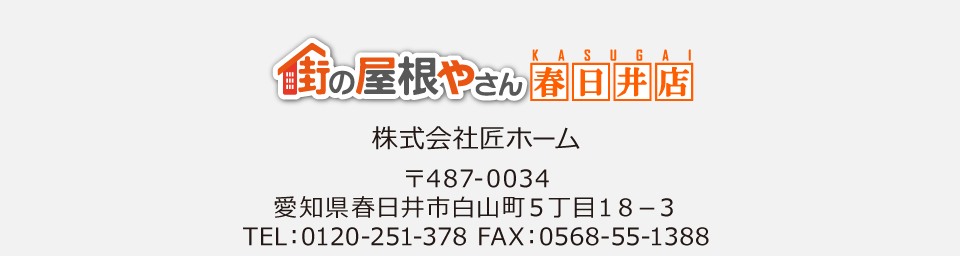2026.02.08
小牧市のみなさまこんにちは。街の屋根やさん春日井店です。 今回は、小牧市周辺で増えている大型倉庫・工場のスレート屋根からの雨漏りについて、実際の現地調査内容をもとに大波スレート屋根のカバー工法(重ね葺き)をご紹介します。 梅雨時期や台風シーズンになると、工場・倉庫のスレート屋根か…
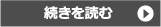

犬山市のみなさま、こんにちは!
街の屋根屋さん春日井店です。
今回は、築100年の古民家における瓦屋根の全面葺き替え工事の様子をご紹介いたします。
長年の風雨や地震の影響により、瓦が落下し、屋根に穴が空いてしまった状態でした。
桟瓦や大棟のゆがみも目立ち、しっかりとした補修では対応しきれないことから、全面的な葺き替えが必要となりました。
古民家の瓦屋根の工事は、構造の確認や下地の補強なども含めて大掛かりな作業になりますので、
工程ごとに段階的にブログでご紹介しております!
ぜひ、下記リンクより各工程もご覧ください!
🔽 古民家平屋瓦屋根全面葺き替えのブログも合わせてご覧ください 🔽
【第2弾】
👉 犬山市の皆さまへ古民家平屋の瓦屋根垂木補修交換作業第2弾
【第3弾】
👉 犬山市の皆さまへ古民家平屋の瓦屋根を全面葺き替え工事実施第3弾
【第4弾】
👉 犬山市の皆さまへ完成間近の古民家屋根補修瓦葺き作業第4弾
【最終回・完工編】
👉 古民家平屋の瓦屋根に穴が!全面瓦葺き替え工事がついに完工【犬山】

写真をご覧いただくと、屋根の最上部「大棟(おおむね)」が鬼瓦から見て真っすぐではなく、歪んでしまっているのがわかります。
さらに、屋根の平部にあたる桟瓦(さんがわら)も、波打つようにうねりが出ている状態です。
このような症状は、瓦そのものが原因ではなく、瓦を支える「垂木(たるき)」という木材が老朽化し、沈みや折れが発生しているために起こります。
古民家の瓦屋根は長年の風雨や経年変化により、下地構造ごと劣化していることが多く、表面だけでなく骨組みからの見直しが必要となるケースが少なくありません。

次は瓦の撤去作業の様子をご紹介します。
まずは屋根の古い瓦を一枚ずつ丁寧に剥がしていくところからスタートします。
写真をご覧いただくとお分かりの通り、屋根の下地となる垂木(たるき)には腐食や歪みが見られ、足場が非常に不安定な状態です。
一歩踏み外せば足が屋根を突き抜けかねないため、作業員は足元を慎重に確かめながら、一列に整列して人の手で瓦をリレーのように渡し下ろしていきます。
手間はかかりますが、今回は建物のすぐそばにトラックを停められるスペースがあったため、コストを抑える方法を選択しました。
また、軒先(雨樋のあたり)を見てみると、左側に傾いているのがはっきりと分かります。
これは屋根全体の下地構造が経年劣化している証拠であり、単なる瓦の修理ではなく、しっかりと下地から葺き替える必要がある状態です。

大棟(屋根の一番高い部分)から右側の瓦撤去作業が完了しました。
撤去した瓦は非常に重く、ここまでの作業だけで2トントラックの荷台が満載になるほどの量になっています。
長年風雨にさらされてきた古民家の瓦屋根は、枚数も多く一枚一枚が重いため、安全かつ効率的に作業を進めるには技術と経験が必要不可欠です。

屋根土(葺き土)の撤去作業の様子をご紹介いたします。
こちらの古民家では、屋根全体に土がぎっしりと敷き詰められた「べた葺き」と呼ばれる工法が使われていました。
屋根土は長年風雨や湿気を吸って固まり、非常に重くなっているため、ハンマーを使って砕きながら丁寧に取り除いていきます。
土の下には、下葺き材として「わら(茣蓙のような素材)」が敷かれており、土と混ざってしまっているため分別にもかなり手間がかかります。
このような古民家では、わらのほかにも杉の皮などの自然素材が使われているケースが多く、屋根の構造や工法をしっかり見極める必要があります。

この土葺き(つちぶき)とは、昭和初期ごろまで一般的だった瓦屋根の施工方法で、別名「湿式工法」とも呼ばれています。
まず、屋根の下地である野地板(のじいた)の上に、杉の皮やわらなどの下葺き材を敷き、
その上に粘土(屋根土)をたっぷりと敷き詰め、その粘土の重みと接着力で瓦を並べて固定するという方法です。
このように屋根全体に土をしっかり敷く「べた葺き」は、
断熱性や防火性に優れている反面、瓦と土の重量が構造に大きな負担をかけるというデメリットもあります。
興味深いのは、当時の土葺きでは瓦が一切固定されていなかったという点です。
実はこれ、地震対策だったんです。
揺れが強くなった際に、あえて瓦が屋根から落ちることで、建物全体が倒壊するのを防ぐという考え方がされていました。
崩れてしまった瓦は、再利用も可能でしたし、傾いた建物も直しやすかったため、地震に強い知恵として活用されていたんですね。
現在では、耐震の考え方が変わり、屋根を軽量化して建物への負担を減らす方向へとシフトしています。
そのため、土葺き工法は関東大震災以降、徐々に使われなくなってきたのです。


こちらは、屋根に大きな穴が開いていた箇所の様子です。
古い瓦・葺き土・わら・野地板をすべて撤去したところ、下地となる垂木(たるき)が折れてしまっており、その下にある梁(はり)も腐食している状態でした。
さらに、他の部分の垂木にも補強として継ぎ足された跡が多数見られ、構造的な強度がかなり低下していたと考えられます。
古民家では築年数が長いため、このように内部構造が予想以上に傷んでいるケースも少なくありません。

こちらの現場では、屋根の下葺き材として「わら」が敷かれていたのですが、さらにその下を確認すると、なんと野地板の代わりに竹が組まれていたのです。
写真の手前部分をご覧いただくと、すでに野地板が撤去された箇所に竹がしっかりと組まれており、当時の施工方法の特徴がよく表れています。
このように、古民家の瓦屋根には現在では見られない構造や素材が使われていることも多く、丁寧な調査と対応が必要になります。


作業終了時には、雨が入らないよう屋根全体にブルーシートをしっかり張り、胴縁で仮止めして本日の工程は終了です。
これで、雨の心配もなく安心して次の作業に進めます。
次回は、この屋根の反対側も同様に撤去作業を行っていきます。
築年数がある古民家は作業量も多く大変ですが、ひとつひとつ丁寧に進めてまいります。
「犬山市で古民家の瓦屋根の葺き替えを考えている」「全面的にメンテナンスしたい」という方は、
ぜひ街の屋根屋さん春日井店までご相談ください!
今後もブログで工程をご紹介していきますので、屋根が美しくよみがえる様子をぜひお楽しみに♪
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん春日井店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.