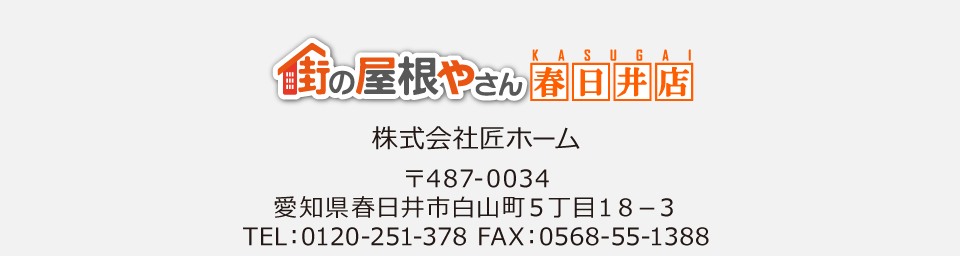2026.01.15
春日井市のみなさま、こんにちは。街の屋根やさん春日井店です。 今回は、瓦屋根の棟下などに施工されている「漆喰(しっくい)」の役割や必要性、正しい修理方法について、屋根専門業者の視点から分かりやすく解説いたします。 軒先や庭先に白い粉・欠片が落ちている 屋根の漆喰が剥がれてきている…
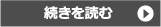
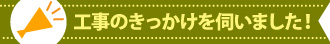
雨漏りして室内の天井にシミが出来ていました







建物:木造戸建て、築43年、1階屋根の棟部で雨漏りの兆候あり。
症状:棟下からの雨染み、小屋裏検査での雨跡。棟瓦のズレ・目地(葺き土)の崩れが確認できる状態。
下地:既存の葺き土は風化・流出が始まっており、防水性が低下。棟内部の下地(桟木・垂木・貫)に腐食の兆しがないか念入りに調査しました(今回大きな腐食は見られませんでしたが、一部補強が必要な箇所を処置)。
現場での初動調査は、必ず屋根の全面確認・小屋裏点検を行い、雨漏りの原因が棟だけかどうかを判別することが重要です。



既存棟瓦の撤去
棟瓦を一列ずつ慎重に外し、瓦の状態(再利用可能か)を確認。割れているものは廃棄、良好な瓦は再使用可能な場合は洗浄保管。
葺き土(古い漆喰・下葺土)の撤去
長年の葺き土を完全に取り除き、棟内部まで清掃。古い葺き土は風化しており、防水機能は期待できません。
下地の点検・補修
桟木(さんぎ)や貫(ぬき)、隅棟の下地材を点検。腐食・スカスカの部分があれば交換または補強を実施。本現場は一部補強で対応しました。
モルロックによる積み直し(新たな棟下地)
モルロック(改良モルタル材)を用いて棟の新規積み直しを行います。モルロックは適度な粘度と強度があり、瓦との密着性が高く、従来の葺き土より劣化しにくい特長があります。混合(水との割合)や打設厚さを職人が管理して施工。乾燥養生期間を確保して強度を出します。
棟瓦の復旧(固定)
モルロックが所定強度になった後、棟瓦を丁寧に被せていき、瓦どうしの納め、面の美しさを調整。必要に応じて専用固定金物やステンレスビスを併用し、瓦の飛散防止を確保します。
仕上げ・清掃
目視での最終チェック、雨仕舞確認、周辺清掃を行い作業完了。



モルロックは改良モルタル系の下地材で、従来の葺き土(粘土系)と比べて風化に強く、固化後の強度が高いため棟の安定に優れます。
葺き土は素材自体が流出・風化してしまうことがあり、長期的な耐久性に課題が生じます。モルロックはそれらの欠点を解消し、雨仕舞(あまじまい)を長く保つ目的で選定することが多いです。
ただしモルタルは硬化後にヒビ割れが起きる可能性もあるため、施工時の厚み管理・収縮対策(ワイヤーメッシュ併用や適切な配合・養生)が重要です。


下地の確認を怠らない:棟は屋根の要。下地に腐食があると短期で再発します。必ず小屋裏からの点検も実施。
施工時の気温・湿度管理:モルタル系は乾燥条件で強度が左右されるため、適切な養生が必要。真夏や真冬の施工は配合・養生管理が重要。
瓦の再利用可否判断:割れや吸水で劣化した瓦は再使用不可。見た目だけでなく強度を確認。
漆喰との使い分け:地域や屋根形状によっては、モルロック+漆喰の併用や、ステンレス金具との併用が有効。
通気と温度差:棟部に通気を確保する場合は、施工計画段階で換気口の確保と雨仕舞の両立を検討。

適切に施工されたモルロック積み直しの棟は、10〜20年程度を目安に雨仕舞が持続することが多いです(施工品質・気候条件により差あり)。
年1回の目視点検(棟瓦のズレ、目地の割れ、瓦の浮き)を推奨。雨漏りの兆候(雨染み、小屋裏のシミ)を見つけたら早めの点検を。
Q1:葺き土のまま補修してはいけないの?
A:葺き土は伝統的な工法ですが、風化や流出が起きやすく、再発リスクが高い場合があります。長期的に見てメンテナンス頻度を減らしたい場合はモルタル系(モルロック等)をおすすめします。
Q2:費用はどれくらい?
A:棟の長さ、棟の高さ、下地の状態(補修が必要かどうか)、使用材料で変動します。簡易な積み直しであれば概算見積りで対応可能ですので、現地調査のうえ詳細見積をご提示します(まずは無料調査をご相談ください)。
Q3:工事期間は?
A:一般的な住宅で1日〜数日(乾燥養生を含めると数日〜1週間程度)です。天候や下地補修の範囲により変動します。
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん春日井店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.